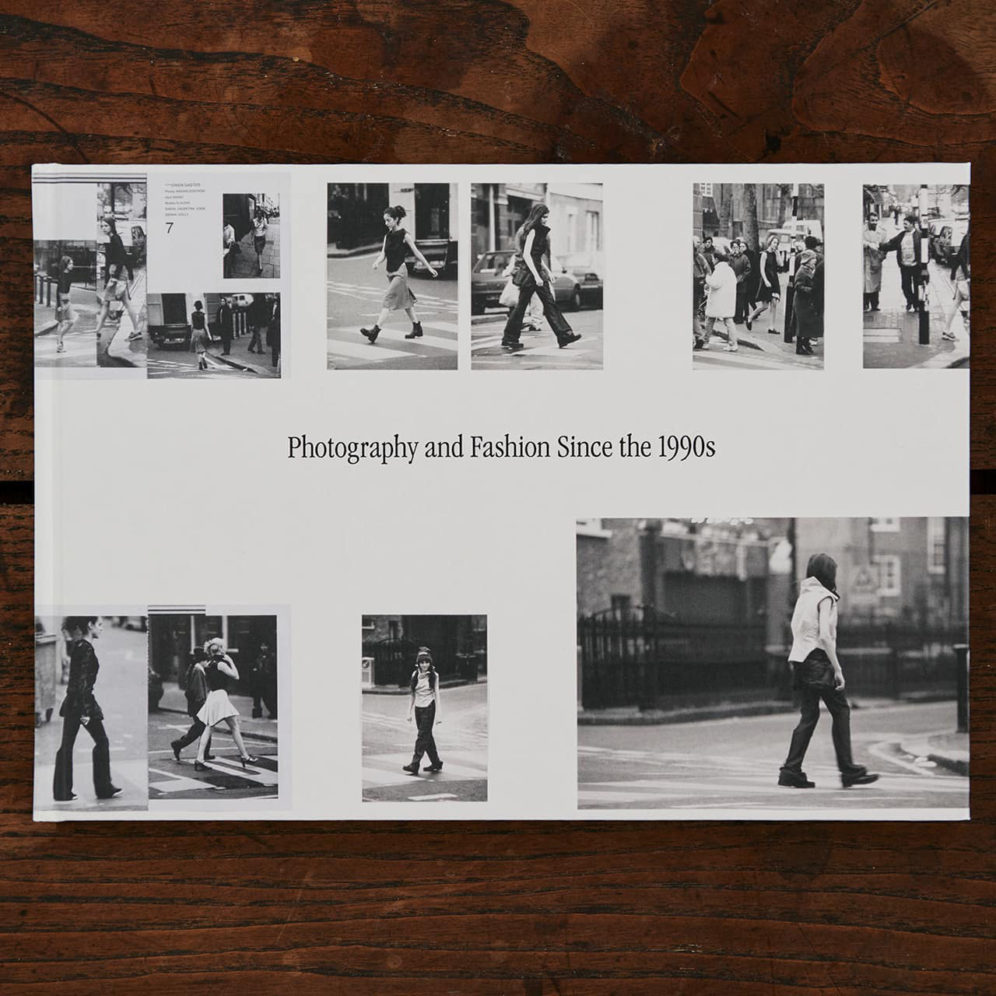「来たるべきグラフィックデザイン
のための図書室」に寄せて
「来たるべきグラフィックデザイン
のための図書室」に寄せて
「来たるべきグラフィックデザイン
のための図書室」に寄せて
初めに読んだ保坂和志の小説は『小説の自由』で、これは小説ではなく、小説論なのかもしれないが、その後に遡って読んだ『カンバセイション・ピース』でも同じように、そこではずっと思考が漂い、止まることがない。ページの角を折り、アンダーラインを引いたところを読み返してみるが、すでに私はそこにおらず、全体の1/3ほどの角を折っているので、小口が盛り上がってしまっているだけだ。 どう「読ませるか」(見せるか)ではなく、どう「読んでいるか」(見ているか)。家への帰り道でふと木を見つめるような、その思考の中でしか語られないものがあり、それはそのまま日々「生きる」ことだと思う。 何かを読んだり、見たりしたとき、祖母を思い出す。2014年に亡くなった祖母が生き続けていると感じる。それは誰とも共有できない。誰とも共有できない思いのようなものが、私以外の誰かにも起こっている。そのとき、書く(描く)人と、読む(見る)人は、一緒にいる。 (『idea #382』「グラフィズム断章:もうひとつのデザイン史」より)