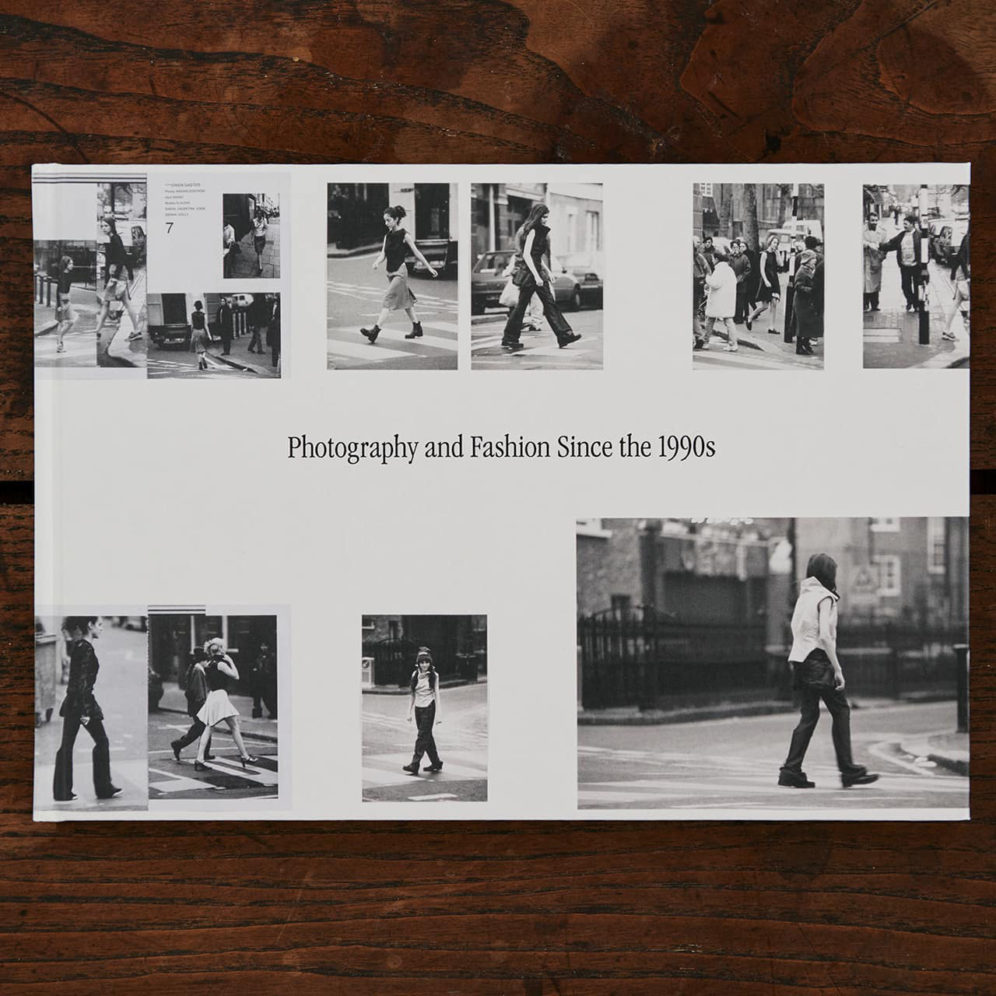呼んでいる本
現代フットボールが語られる時に、“ポジショナルプレー”という言葉をよく耳にする。チェスなどのボードゲームで使用される言葉だが、乱暴に言ってしまうと、ピッチを縦横のラインで区切ることにより、位置(ポジション)に応じたタスクを明確にする、ということになる。そこでは、人とボール、その位置と関係が常にめまぐるしく動いていく。優れたフットボーラーは、そこで「何が起きているかを把握しながらプレーする」のではなく、チェスのプレーヤーが盤を見るように「スペースと人を動かしながらプレー」する。つまり「位置」と、その「運動」を捉えることで、「時間」を生み出していく。
「休止」を意味する“ラ・パウザ”という概念があるが、数秒後に起きることを明確にイメージし、そこから逆算してプレーする名手たちを指す。私自身、十代をサッカーに明け暮れた身として、もう少し偶発的なものではあるが、何度か経験がある。こうしてシュートを打てばゴールすることができる、ではなく、「あ、ゴールした」とシュートを打つ前に思い、その通りにボールがゴールに吸い込まれていく――。
神経生理学者ベンジャミン・リベットによると、行動を起こす際、脳に起こる電位の、約0.5秒後に「意識」が生まれているという。それはつまり、私たちが何か行動を起こそうとするより前に、既に行動の萌芽があり、(事後的に)「そうしよう」と思う、ということだ。ではなぜ、私たちはまるで「自分の意思」で何か行動を起こしている、と感じるのだろうか。それは、意識の発生後、主観的な時間の繰り上げが起きているためだという。つまり、意識はまだ生まれていないが、脳が無意識のうちに反応し、その瞬間に「意識した」と、時間を遡って経験される。
「意識はその持ち主に、世界像と、その世界における能動的主体としての自己像を提示する。しかし…意識が生じる約〇・五秒前から、体のほかの部分がその感覚の影響を受けていることを、意識は知らない。…意識は、行為を始めているのが自分であるかのような顔をするが、実際は違う。現実には、意識が生じる前にすでに物事は始まっている。」『ユーザーイリュージョン 意識という幻想』(トール・ノーレットランダーシュ著/紀伊國屋書店刊)
書店でふと手に取った「その本」が、頁を開く前から自分にとって大事な本だと分かるのはなぜだろうか。もっと言えば、書店の門をくぐった時点、「その本」と私の距離がまだ数メートル離れているにも関わらず、既に私は「その本」と出会っている。
私たちは、例えば雨の落ちる様を見たり、その粒を手のひらに感じることができるが、目の前にある果物が少しずつ朽ちている姿は見ることはできない。しかし、本当にそうだろうか。考えてみれば当たり前だが、果物も(この眼や手が気がつけない速度で)緩やかに、そして分子レベルでは常に変化している。
田中義久は、「紙」「インク」「文字」「図像」、そうした要素とその位置を、分子レベルで見て、触れるのではないかと思うことがある。それは、つまり「時間」を操る行為だ。フットボーラーのように、ピッチを鳥のように眺め、人とスペースを動かし、なかった「時間」を作る。脳と意識の間にある0.5秒に入り込み、見えないはずの紙上のインクの動き、そして(後に触れることになる)その手触りを経験として先に届ける——。
私にとって、「その本」は、写真家津田直の作品集『SAME LAND』(limArt刊/三部作として『NAGA』『IHEYA・IZENA』がある)だった。素っ気なく、表紙には意味を読み取れるようなものはほとんどない。それでも、私には「その本」が遠くから呼んでいることが分かった。そのガサガサした表紙、ヒエラルキーのない書名と著者名、片手で持つことのできるサイズと重さ、本文用紙のコシとインクの染み具合。私は「その本」を遠くから読んでいたのである。開くと、美しい写真が並ぶ本だったが、私はそのことを知っていた。
(『idea #381』「越境の遍歴 田中義久のパースペクティブ」より)